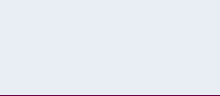小説
「War? Gameres」
いよいよ始まります。
公言するのが、憚られるコーナーなので、このページを発見した人は、決して友達になど教えたりなどしないでください。
で、始まりはするのですが、暇つぶしに書いているだけですので、いつまで続くとか、どこまで続くとか、落ちはどーするのとか、定期的にアップできるのか、とかとかとか、全く考えていません。
ついでにいうと、このコーナーに関しては、別に感想も全く持って求めていません。
自慰的な文書ですので、のぞいてしまった人は、そっと頬を赤らめて、そっとして置いてください。
というわけで、頬を赤らめられる人だけ、続きを読んでいってください。
というわけで、始まり、始まり……

どうしてこんなことになったんだろう。
「そっちだ。右から回り込め」
夕暮れ時の森の中、僕は木の幹に背中を預け、動悸も激しい心臓を押さえながら息を殺し、それでも何度も大きく深呼吸した。
僕の右手には、テレビや映画で兵隊さんが持っているような黒くて長いライフルが握られている。
あたりには銃声が響いていた。
僕はその銃のグリップを強く握りしめた。
額から流れる汗が頬を伝わる。
僕はグローブを付けた手でそれを拭った。
本当なら、今頃は楽しいキャンパスライフを送っているはずだったのに……
本当なら、今頃は楽しい楽しく飲んでるはずだったのに……
本当なら、今日は……
なんであの時、僕は……
「いたぞ」
どこからか、誰かの怒声が聞こえる。
見つかった。
僕の体が一瞬こわばる。
逃げなきゃ。
僕は木の幹から体を起こそうとした。
そのとき、少し離れた藪から、一人が飛び出した。慌てた僕は幹にもたれたまま、銃口を彼に向けていた。
そして僕が引き金を引こうとした瞬間、彼は同時に二方向から無数の弾丸を体中に受けていた。もんどりうつ彼の最期の姿を僕は向けた銃口を下げもせずに眺めていた。
彼は僕の味方だった、はずだ。
よく覚えていなかった。
敵も見方も判らなかった。
とりあえず引き金を引かなかったことにほっとしつつも、次こそ僕の番だろうか……と考えた。考えざるを得なかった。
撃たれる彼の姿はもうすぐ訪れる僕の未来に他ならない。
僕は音を立てないようにゆっくりと体を動かした。這ってでもこの場を離れないと今度こそ自分の番なのだ。
湿った草の臭いが鼻につく。地面にこんなにも顔を近づけるのはいつ以来だろう。
僕を捜しているであろう敵の足音を感じながら、そして僕をあぶり出すために時々ばらまかれるように撃たれる銃の射撃音にビクつきながら、僕はゆっくりゆっくりと動いていった。
敵の足音が少しずつ僕から離れていく。
ような気がした。
違う場所を探しに行ったのだろうか。
期待と希望が交じり合う。
僕はうつぶせのまま、安堵のため息を漏らした。
そのとき
「フリーズ!!」
少し高い声が僕の上から聞こえた。
「動けば撃つ!! 降伏か死を選べ」
腹這いの僕の背中に堅いモノが押しつけられてた。
銃口だ。敵は去ってなんかいなかった。
さっきの男のやられ方が脳裏をかすめる。
このまま僕も死ぬのか?
撃たれたら痛いんだろうな。
ああ、このまま無様に死ぬのはイヤだ。
僕はグリップを握りしめ、
声にならない叫び声を上げ、
体を回転させ、
自分の唯一の武器であるライフルの銃口を敵に向けた。
僕が降伏すると思っていた敵の銃口は、僕が身を返したために僕の背中からはずれていた。が、それでも体勢は敵に有利だった。
僕が引き金を引き絞ると同時に相手の銃口からも無数の弾丸が打ち出されていた。
身が白くなるような鋭い痛みが腹から胸から無数に突き抜ける。
それは恐らく相手も同じなのだろう。
時間にすればほんの数秒、いや、一秒もなかったに違いない。
でも、僕にはすごく長く感じられた。
すごく長く感じられたんです。
……………
「ヒ、ヒット」
「ヒットォー」
僕も相手も痛みにこらえながら大きな声を上げ、ライフルごと両手を上に持ち上げた。
姿は見えないが、くすくすと言う笑い声の気配があちこちから聞こえてくる。正直、何故笑われているのか僕には見当も付かない。
「終ー了ー。Bチームの全滅でーす」
遠くから大きな叫び声が聞こえる。
どうやら僕が最期の一人だったらしかった。
僕は打ち合った相手の差し出す手に捕まって立ち上がり、撃たれた場所をさすりながらそのまま相手の後ろについて休憩所まで歩いていった。
「あー、もう間抜けだよねぇ。相手に銃口突きつけるとかしちゃ駄目だって理由が、よーくわかったよ」
僕の前を歩いていた敵は死体置き場と呼ばれる休憩所に来ると、フルフェイスマスクを外し、長髪をしまっていた帽子を脱いで、僕の方を振り返って笑った。
それはそれは豪快な笑みで、それはそれは汗だくの笑顔で、それはそれは爽快そうだった。
僕の方は言葉の意味がわからないままだったが、とりあえずその笑顔につられて、僕に痛い目を合わせてくれた相手なのに、その可愛さにつられて、やっぱり笑顔を返してしまっていた。
彼女こそ、僕をこの戦場につれてきた張本人だった……
|

昭和八十三年四月
姓は山田、名は錦。
彼はこの度めでたくも無事大学入試をクリアーし、無事大学生となっていた。もっとも、決して高い偏差値を必要とされる大学では無かったが、一応は国立大学だし、田舎とはいえその分、家賃も安く一人暮らしもできることとなった。
引っ越しなどでバタバタとはしたものの、ワンルームに運び込む荷物はそんなに多くはない。荷ほどきも済み、新居で暮らすに当たって必要なモノもすでに買い込んだ。
まだ着慣れないスーツに袖を通して、締め慣れないネクタイを締め、入学式も無事済んだ。
春の大学、晴れの大学。
前途は意気揚々。といっても何かを成したくって大学に入ったわけではない。
このまま高校を出て働く気にはなれなかったし、何となく進学を選んで、何とか入れそうな大学を選んで、何とか一人暮らしの権利を勝ち取っただけなのだ。
あえて言うなら、何もしない自堕落な生活がしたくって大学に入っただけの学生であった。そして少しだけ何かが変わるんじゃないかという期待を抱いている学生だった。
入学式の後、大教室で卒業までの単位の取り方や授業の選び方などのシステムの説明を学生課の職員に講義された。が、そんなのは上の空だ。なにも彼に限ったことではない。彼の周りの新入生の誰もがそんな状態だ。
スーツを着こなしているやつもいれば、普段着のやつもいる。えてして女の子はみんなおしゃれに見える。
猛者の中には早速、声をかけているやつもいる。
「ケッ、お前等人の話を聞けよ」
錦は自分のことを棚に上げ、彼からしてみれば猛者である奴らに心の中で悪態をついた。
この世に生を受けて一八年。もちろん彼女なんてのがいたことはないし、クラスの女子とも必要最低限以外に親しくはなしたこともない。
大学に入れば、少しは自分を変えてみよう。
そう思っていたはずだった。
錦は軽くため息をつき、分厚い冊子をパラパラとめくった。配布された紙袋の中には、その他にもいくつかの小冊子が入っており、その中の一冊に学内クラブの紹介冊子があった。
退屈な単位の取り方の講義に飽きていた錦は、そのクラブ紹介の冊子をめくり始めた。周りを見てみれば、自分と同じようにすでに講義に飽き、その冊子をめくっている奴もいた。
いろんなクラブがあるもんだな。
よくあるような文化系、体育会系のクラブもあれば、お決まりのサークルもある。
各クラブに一ページが当てられ、どの部の紹介も新入部員を募集する記事と、活動内容が書かれている。
特に入りたい部活があるわけではない。
高校時代にも何部にも入っていなかった。
女の子と仲良くなるには、サークルにでも入った方がいいのだろうか。無難にテニスサークルにでも入るべきだろうか。
スポーツはこれといってやった記憶がないので、体育会系のクラブには興味が沸かなかった。あまり熱血するのは性に合わないし、それにどちらかというと運動は得意ではなかった。いや、むしろ苦手だった。
その点、サークルなら、気軽か。いっそ、文化系なら知的なお姉さんがいるかも。
想像は膨らむ。が、やはり肝心の自分にやりたいことも得意なこともないので、どの部もピンと来なかった。
錦は本を閉じ、机に顔を埋めた。
「なあ、君はどこの出身」
しばらく机に頭を付けて退屈そうにしていると、隣に座っていた男が声をかけて来た。
それはやたらと体格の良い男だった。
「俺? えーと、大阪やけど」
「そうなんだ。俺は名古屋から」
で、だからどうなんだという話だ。
「俺、前藤っていうんだけど」
「俺は山田。山田錦」
お互い自己紹介をすませると、微妙な沈黙があった。
「退屈な話だよね」
恐らく立ち上がれば一八〇センチはあろうかという大きな体に、大きくて少し厳ついめの顔の前藤と名乗った男は、それでも精一杯なのであろう緊張した笑顔を錦に向けた。
「そうだよね」
正直、身長一六〇センチと少しの錦にしてみれば、得体の知れない大男は苦手なタイプだった。が、敵意はなさそうだし、むしろ好意的に努めているのは感じられた。
「さっきから、山田君が見てるその本って、どこにあるの?」
「入学式で会場を出るときに配られた袋の中に入ってたけど」
錦に言われて、彼はもう一度、自分の紙袋の中をすべて机の上に広げた。
「あ、あった」
「良かったやん」
前藤は錦に嬉しそうな笑顔を見せた。
「うわー、いろんなクラブがあるね」
冊子をめくりながら前藤はまた嬉しそうな笑顔を見せた。
なりは大きいが子供みたいな奴だな。
とはいえ、自分も同じことを考えていたのだ。
「どのクラブに入るか迷うよね」
「そうだね」
「山田君は、決めてるの?」
「いや、別に……えーと、前藤君は?」
体育会系だろうな。
と錦は思った。
「うーん。全然考えてないな」
「高校の時は? その体格だと、スポーツしてたんでしょ」
「うん。高校では柔道部にいたよ」
やっぱり
「大学では続けないの」
前藤は少し顔を曇らせ、それから少し恥ずかしそうに笑った。
「いやー、もういいよ。大学の格闘技系は厳しそうだし、僕は高校でも補欠だったから」
「ふーん」
「山田君は高校は」
「帰宅部。なんにも入ってなかったよ」
「そうなんだ」
何故か前藤は嬉しそうに笑った。
「今日と明日が、クラブ勧誘日らしいんだけど、あとで一緒に回らない? できたら明日も」
錦にも特に予定はなかったし、このまままっすぐ家に帰ってもやることはなかった。
何より、このまま一人で帰ると、ずっと一人でいるような気がしたので、しばらく考えた後、
「いいよ」
前藤の申し出を受けることにした。
その前藤は錦の返事を聞いて胸をなで下ろした。
「ありがとう。実は随分前にこっちに出て来ちゃってて、知り合いもできないし、一人暮らしだから話し相手もいないし、まいってたんだ」
そう言えば錦自身は二日前にこっちに来ていたが、引っ越しの片づけで一杯一杯だったため、誰とも会話をしていなかったことすら忘れていた。
普段はどちらかというと人見知りな自分が、誘いに簡単にのったのはその為か。
そう思った。
「疲れたわ」
「そうだね」
二人はベンチに腰を下ろしてため息をついた。
今日は入学式翌日。勧誘日二日目だ。
昨日、あれから二人で学内を歩いたのだが、どこに行っても配られるビラを受け取らされ、呼び込みをかけられてばかりで、何部が何部なのかわからなかった。
なにより、前藤の体格のため、体育会の勧誘が多かったようにも思われた。
そういうわけで、結局昨日は早めに大学を離れ、近くのファミレスで二人でクラブ案内の冊子を読みふけっていたのだ。ちなみに学食を使わなかったのは、学食で案内冊子など見ていようものなら、すぐに諸先輩方が来て勧誘してくるからだ。なにより、入学式のスーツのままでは、新入生であるのがバレバレで、格好の的である。
というわけで、今日は二人とももちろん普段着だし、案内冊子も家に置いてきた。
それでも、新入生であることはその挙動から在学生にはバレバレなのだが。
「昼飯、どうする」
「学食に行ってみる?」
危険な気もしたが、行ってみたい気もする。
二人とも朝食を摂っていなかったし、文化祭でも開いているかのような学内の活気に疲れていた。
学食には、第一と第二があり、大きい方が第一である。理由は安くてボリュームがあって利用者が多いからだ。当然、二人はそんなことは知らないが、人の流れにそってたどり着いたのが、第一だった。
食券制度になっているらしく、販売機の前には長い行列ができていた。
行列の中には袴姿や、ジャージ、そろいのトレーナーなど、部活の格好をしている学生もいた。
高校とは違いやたらといる人の数、そして広い食堂に二人は顔を見合わせた。
これから、恐らく毎日ここで昼食を摂ることになるのだ。
とりあえず二人ともAランチにして、開いているテーブルを探した。
都合良く席は見つかったが、長いテーブルにはジャージの人たちも座っていた。
声はかけられたくないな。と思いながらも、やっと見つけた席だ。早く座らないと、誰かに座られてしまう。
二人は意を決して席に着いた。
幸い、勧誘をしては来なかった。
ただ、彼らの会話は自然と耳に入ってきた。
「水泳部の奴ら、水着作戦で今年も大量確保らしいぞ」とか
「テニスのスコート戦線もきてるらしいぞ」とか
「今年の文芸部はカジュアル路線で攻めるつもりだ」とか
「以外とアニ研が数字を伸ばしてるらしい」とか
他のクラブの新入生獲得状況を報告し合っていた。
肝心の彼らはというと、おそろいのジャージを着ているにもかかわらずその背中には(MAN-KEN)の文字がプリントされていた。
って、漫画研究会か。
錦と前藤はお互い小声で話し合った。
「真剣に勧誘してるところもあるけど、あくまで勧誘っていうお祭りを楽しんでるみたいやな」
「そう言えばそうだね。勧誘も余りしつこくないし」
二人は少し気を軽くした。
空腹が満たされたおかげもあったのだろ。
「どっか見てみたい所とかある?」
「うーん……水着作戦とか、スコート戦線は正直気になるなぁ」
二人はお互いの目を見て笑った。
「水泳部ってどこで勧誘してるのかな」
「そう言えばテニスって、クラブとサークル二つあったはずだぞ」
二人は広場で辺りを見回していた。
案内冊子は家に置いてきている。
「でも、勧誘するなら、メインストリートだろ」
勧誘は学内のあちらこちらで行われてはいたが、ブースが作られているのはあくまで学内中央を正門から広場までを縦断している「花道」と呼ばれるメインストリートに限定されていた。
「また、あの人混みの中に入るのか」
「お祭りだと思って楽しむしかないよ」
まあ、実際まだ履修届も出していない現在、勧誘する側も決して本気で勧誘しているわけではなかった。あわよくば今日入部する奴がいればラッキーなことだし、落ち着いてから入部しに来るにしても、今のうちに名前くらい覚えて置いてもらおうというところだ。
それにどのクラブも勧誘会の後には飲み会があるわけで、今日のことを肴に飲むのだから、可能な限りお祭り騒ぎをして、ネタを作っておこうと言うことだ。それに体験入部と称して新入生を今晩の飲み会に連れて行ければ、それもまた楽しいという程度のことだ。
だから、まだ肌寒いというのに水泳部の女子部員は競泳用とも思えない水着を着ていたりするわけだ。
だから錦と前藤もやっと見つけた水泳部のブースで鼻の下を伸ばしていた。
「君は、いい体格してるなぁ」
いきなり、誰かが前藤の肩に手を回し、大声で話しかけてきた。
驚き慌てた前藤は手を払いのけて声の主を振り向いた。
そこには自分よりも背が高く、肩幅も胸板もある色黒の大男が笑っていた。
「そっちの君もいい体格だぁ。いいコックスになれるぞぉ」
男は錦にも見下ろして笑顔を向けた。
コックって、料理クラブか何かか? にしてもデカイな。
不安そうな顔をする二人に大男は更ににっこり笑いかけた。
しかし、少し不気味だった。
「コックって、何ですか」
「お、興味あるかぁ」
「いや、そうじゃなくって……」
「まあ、いいさぁ。ふ、ふ、ふ」
男は二人に背を向け、ジャージのバックプリントを親指で指さした。
「栄光ある我がボート部にようこそ」
「いや、ようこそって」
大体、質問の答えになってないし……
「体格のあるそこの君は練習次第でレギュラー確実だぁ。小さい君も、その体格を活かしてコックスになってみないかぁ」
「いや、あんまり料理は……」
「違うぞぉ。コックじゃない。コックスだぁ」
「だから」
「コックスというのは、ボートの舵取りをし漕ぎ手への指示を出したりする役のことだぁ。これがなかなか大事な役目なんだなぁ。うん」
大男は手に持っていたビラを二人に差し出した。
「興味あるかぁ」
「いや、僕たちは……」
「そうかぁ、興味あるかぁ。じゃあ、もう少し詳しくはなしてやろう、こっに来い」
二人の断ろうとする言葉に耳も貸さず、大男は二人の首に腕を回してきた。ふりほどこうにも凄い力でほどけない。
ボート部のブースは水泳部のブースから大して離れてはいないようだった。
「ほらほら、速く歩けよぉ」
とりあえず話を聞くだけなら……
いくら頑張ってもふりほどけない大男の腕に錦が諦めたとき、一方の前藤は何とかそれを振りほどいた。
「いや、僕はもう入りたいところを決めてますから。失礼します」
彼はそういうと、頭を下げてそそくさと人混みの中に消えていってしまった。
ま、マジか。
大男の脇に首を挟まれたまま、錦は自分を見捨てていってしまった前藤に言葉を失っていた。大男の方も前藤を追おうとしたが、錦を抱えたままではさすがにそれも叶わなかった。
「まぁ、やりたいことがあるなら仕方がないなぁ」
大男は錦を見下ろして、また笑った。
そんなの嘘に決まってるだろうが!!
錦の心の叫びが彼に聞こえているはずもない。口に出した言葉も聴いてないのだから。
そして、あれよあれよと引きずられているうちに、とうとうボート部のブースにたどり着いてしまった。
ああああ。
「いよう。お前等、新入部員候補だぞぉ」
「ちぃっす」
一斉に全員が振り向き、挨拶する。
「話を聞いてくれるそうだぁ」
「ようこそ。ようこそ」
すぐに女子部員がやってきて、大男の脇から解放された錦に椅子を勧めてきた。
ショートヘアーのかわいらしい人だった。
座ったら、駄目だ。座ったら、最期だ。どうする……
錦は女子部員の笑顔につられ腰掛けそうになりながらも、何とか踏ん張った。
やりたいことがあるなら仕方がないなぁ。
さっきの大男の言葉が不意に頭を横切った。
「いや、実は僕も他に考えてるクラブがあるんですよ」
通じないかもしれないが、うまく行けば……
慌てて話す錦の顔を見ながら、女子部員はもう一度にっこりと、優しい笑顔を浮かべた。
「本当に?」
優しい笑顔に小心者の錦の心はチクリと痛んだが、このままボート部員にされてしまってはかなわなかった。
「は、はい」
「うーん。そっかぁ」
彼女は残念そうな顔をしたが、やっぱり笑顔でいてくれた。そして後ろを振り返ると、
「長沼さーん」
ブースの後ろでスポーツドリンクを飲んでいるさっきの大男を大きな声で呼んだ。
「んん、なんだぁ。どうしたぁ」
「この子、他に入りたいクラブがあるって言ってますけど」
「そうかぁ。で、それがどうしたぁ」
「どこから、連れてきたんですか?」
「水泳部で鼻の下を伸ばしてたぞぉ」
鼻の下を伸ばしてたと言われ、錦は少し恥ずかしくなった。
「水泳といえば、水。水といえばボートだろう」
どーいう理屈だ。
「あー、はいはい。つまり、水泳部から拉致って来たわけですね」
「人聞き悪いなぁ。俺は、」
「うるさい!!」
大男がまだ話しているうちに、彼女は彼の向う脛を思い切り蹴り飛ばした。
フガっ!!
「そういう勧誘しちゃだめだって、散々話したのに、少しは人の話を聞いてください!!」
耳たぶをつまんで彼女は長沼に叫んだ。
「ごめんなさいね。馬鹿な先輩が迷惑をかけて」
「いえ」
少し怖いかもしれないけど、いい人……だよな。
「で、もう、そこに入るって決めちゃったの?」
「それはまだ」
「ふーん。何部? 水泳?」
「いや、水泳はたまたまで」
「そっかぁ。まあ、これも何かの縁だから、お茶でも出すから座って待っててよ」
「はぁ」
そう返事して錦が進められるまま椅子に腰掛けようとしたとき、いきなり誰かが錦の後ろ頭をたたいてきた。
「こんなところで何してるのよ! 早く行かないとみんな待ってるじゃない」
錦が驚いて振り返るとそこには錦の全く知らない、女の子が立っていた。
でも、相手は自分を知っているのか、少し怒った顔をして、それでも親しげな笑顔を浮かべていた。
誰だっけ‥‥
錦は少しほうけた顔で、女の子を見上げていた。
結構かわいい。っていうか、かなりかわいいよな。‥‥誰だっけ?
「あなたの彼女?」
ボート部の女子部員が、錦を正気に返すように尋ねてきた。
「えっと」
「そうなんですぅ。これから、彼と二人で行くところがあるんですよ」
女子部員のほうに振り返りかけた錦の頭を抱きかかえた彼女は、満面の笑みを浮かべていた。
「アタシ達、急いでるんで。ごめんなさい」
生まれて初めて女の子に抱きつかれて錦はもはや抵抗する気など全く、これっぽっちも、なかった。
「このまま、ここにいたら入部させられるわよ」
やわらかい感触と心地よい匂いに浮かれる錦の耳元で、彼女は小さく囁いた。
!!!
「行きましょ。ね。」
そう言うと彼女は錦を椅子から立たせ、ボート部員に軽く会釈して、その手を引っぱりボート部のブースから立ち去った。
「ここまできたら大丈夫よね。何か飲む?」
第二学食横の自販機の前で、肩にかけたカバンから財布を取り出しながら彼女は錦のほうを振り返った。
「あ。え。じゃ、コーヒー」
「微糖でいいよね」
彼女は同じものを二つ買うと、一つを錦に手渡した。
ベンチに座って飲んだ缶コーヒーは冷たくて美味しかった。
カン!
横を見ると、一気飲みして空になったコーヒー缶をゴミ箱にストライクさせて彼女が笑っていた。で、目が合って錦は慌てて視線を逸らした。それを見て彼女はまた笑った。
「アタシのしたこと、迷惑だった?」
「いや」
「そう。そりゃ、良かった」
大きな瞳がくりくりと動いてニッコリしていた。
誰だろ。
錦は横目でチラチラと彼女の様子を伺っていた。
スタイルは……イイ。顔も……イイ。声も……可愛い。こんな子と知り合いな記憶は全然ないぞ。いくら頭悪くたって、それくらい覚えてるよなぁ。それとも、俺の記憶も定かでないときの幼なじみが今、目の前に現れた。とかって、御都合主義のギャルゲー的展開だってか。ありえないだろう。いや、しかし、こんな子マジで知らないし。ってか、知り合いにはなりたいし……
錦がいろいろ色々考えているだろうことを、逆に彼女の方も伺っているようだった。
で、錦が何かを言いかけたとき、彼女のほうから話しかけてきた。
「本当に入りたいクラブとか決めてるの?」
「いや、実は……まだ。ああ言えば逃げられるかと思って」
「ふーん。でも、せっかく嘘まで付いたのに、そのまま椅子に座っちゃだめだよね」
「そっかな」
「そりゃそうでしょ。それとも、少しはボートに興味あった?」
「いや、スポーツで熱血するのは苦手なんで」
「ふーん。そうなんだ」
彼女は錦を爪先から頭までじっくり眺めた。
「確かに運動が得意なタイプには見えないね」
「いや、そうだよね。うん。ホント。助かったよ。ありがとう」
「で? じゃあ、何に興味あるの?」
そう質問されても即答は難しかった。
「……いや、とくには」
なんだか情けない気がしてきた。
「ふーん」
彼女も少し困った様子だった。
「高校のときは文化系?」
「いや、何にも入ってなかったよ」
「ふーん」
つまらない答えしか出てこない自分に腹が立つ。
それでも彼女はまた、錦の爪先から頭までをジロジロと見つめていた。
「で、今日はどうするの? まだ見て回るの?」
そういえば錦を見捨てた前藤とははぐれたままだった。といっても、今更わざわざ探す気にもならなかった。
「別に無理に今日決める必要もないしね」
「そりゃそうよね」
「だからもう帰るよ」
「じゃあ、この後の予定は何もないの?」
「まあ……」
「ふーん」
錦は見逃したが、彼女の目がわずかにキラーンと輝いた。しかも、どっちかというと悪いことを思いついたときの輝き方だった。
「じゃあさ……」
自分みたいな男にとって又とない出会いであった彼女との別れに名残惜しそうにベンチから立ち上がろうとする錦の袖を、彼女がそっと摘んだ。
「アタシといいことしない?」
我が耳を疑い、錦の体は凍りついた。
ギシギシと首が音を立てながら、ゆっくりと彼女のほうを振り向いた。
「い、い、い、いいいいぃぃ、いいこと?」
「そう」
「き、君と」
「もう、18歳でしょ」
「そ、そりゃあ……」
自分の顔が赤くなるのがわかった。
でもって彼女の顔も赤くなっているのに気づいた。
「じぁあ、」
彼女の顔が近づいてきて、錦の耳元で囁いた。
「黒いモノの先っちょから、白いのいっぱい出してみたくない?」
ブッっ
鼻血が出そうになった。
「興味ない?」
ブンブンブン
錦は今までの彼の人生でかつてないほどに激しく首を振った。
「OKってことでいいのかな?」
錦は今までの彼の人生でかつてないほどに激しくうなずいた。
「じゃあ、付いてきて?」
優しい声で囁くと彼女はベンチを立ち上がり、錦を手招きしながら歩き出した。
もう錦には前を歩く彼女の後姿以外に何も見えていなかった。
お母さん、大学って本当に良いところです。
そして錦は見ていなかった。
前を行く彼女が口元を「ニヤリ」と歪めて笑っていたのを。
「さあ、入って」
「ここは?」
「いいからいいから」
「あ、はい」
そう言ってつれてこられたのは大学の端にある建物の三階、誰もいない静かな部室だった。
彼女しか見えていない錦は部室の扉に何と書かれていたのかも見ていなかった。
普段は雑然としているのだろうこの部屋も今日は綺麗に片付けられていて、荷物には見えないように布が被せられていた。
「まあ、座ってよ」
彼女は部屋の真ん中に向き合って置かれた会議用机の前の椅子に座らされた。
布団は……ある訳ないよな
椅子は安っぽい折りたたみ椅子で、座ると少しギシギシと鳴った。
「えっと」
「大丈夫よ。この時間は誰も来ないから」
誰も来ない。この一言に、錦の冷静さは更に失われた。
「着替えるから少し待っててね」
錦を椅子に座らせると、彼女は部屋の隅に掛けられたカーテンの裏に廻った。
「あ、はい」
ん、着替える?
その言葉に引っ掛かったが、すぐに彼女が服を脱ぐ衣擦れの音、その気配に、全ての思考が停止した。緊張で自分の飲む息の音までがすごく大きく聞こえる。
カーテンの向こうには窓があるらしく、カーテンにうっすらと彼女の影が映っていた。
「覗いたら駄目だよ」
「はい!!」
声が裏返っていた。
「あ、そうそう、」
カーテンの向こうから彼女の手がすっと出てきた。その手には開かれて折り曲げられたノートと可愛いボールペンが。
「これに名前と学部と住所と電話番号、書いといてね」
「はい」
錦は椅子を立ち上がり、駆け寄って彼女からノートを受け取った。
「これって……」
「あー、と……アドレス帳みたいなものよ」
ノートの欄には、すでに何人かの名前が書いてあった。
「これって……」
まさかここに書いてあるやつ全員と……
「あとで連絡取りたくなったら困るでしょ」
「そ、そーだよね」
いまどきケータイに入れときゃ十分なのに……
とか考えかけたが、深く考えるのをやめ、錦は欄の最後尾に言われるままに自分の名前と学部、住所、電話番号を書いていった。
「書けた?」
「ハイ」
また、声が裏返った。
「じゃあ、貸して」
カーテンの隙間からまた彼女の白い腕が伸びてきた。
「ん、確かに。……法学課の山田錦君か。」
そういえばまだ名前も教えていなかったし、聞いてもいなかったことに錦は初めて気が付いた。
「アタシは小麦の麦に、野原の野、愛が芽生えるの芽で、ムギノメバエだよ」
錦の考えを呼んだのか、彼女も初めて名前を教えてくれた。
麦野芽……麦野さん。芽さん。芽ちゃん……
錦は彼女のことを何と呼ぼうか考えた。
「もうすぐ着替え終わるから、もう少し待っててね」
「ハイ」
ん、そう言えば、何で着替えるんだ?
「一つ、聞いていいですか?」
「なに」
錦は勇気を振り絞って聞いてみた。
「着替えるって……コスチュームプレイですか?」
「ぶっ」
カーテンの向こうで彼女が吹き出すのが聞こえた。
何でそんな馬鹿なことを聞いてしまったのか錦にも判らなかった。顔が真っ赤になっていくのがわかった。
「ま、まあ、そんなモンだよ」
それでも、彼女は精一杯笑いたいのをガマンしながら返事をしてくれた。
が、余計に錦の顔は赤くなった。
芽のメイド服姿とか、チャイナドレス姿とか、ネコニャン娘とかを想像してしまったからだ。
「山田くんって、ずいぶんガッコから遠いところに部屋借りたんだね。不便じゃない?」
まだ笑いをこらえながら、彼女が質問してきた。
「いや、大学の近くは高いし、もう埋まってたんで」
「ふーん……通学はバス?」
「いや、バイクです」
「あー、いいなぁ。今度乗せてよ」
「いや、まだ、免許取って一年たってないから」
「違う違う。貸してってことだよ」
「スクーターじゃなくって、中型ですよ」
「大丈夫。アタシも免許持ってるから」
可愛い顔して意外だな。
と錦が天井を見上げて考えたとき、カーテンの向こうから彼女の大きな声が聞こえた。
「よっしゃ。戦闘準備完了」
戦闘って……そんな例えかた……
と思いつつ錦は彼女の現れるカーテンに視線を向けた。
さて、どんなコスプレで出てくるのかと、期待一杯、夢一杯でカーテンが開かれるのを固唾を呑んで見つめた。
シャッ!!
勢いよく開かれたカーテンの向こうから姿を現した芽のコスチュームは錦の想像に無かったものだった。
……軍服。
そう。兵隊さんが戦争するときに着ているあの迷彩柄の服だ。彼女の美しいボディラインを全くもって際立たせることのない、ブカっとしたあの軍服だ。
もっとも、それでも、彼女のやや大きめの立派なバストだけはわかった。
「えーっと……」
錦は何と言えばいいのか判らなかった。
「んーと、えー、あー、」
目をキョロキョロさせているそんな錦を見て、芽は笑いを必死にこらえていた。
「あー、えー……そーいうプレイですか?」
最後の小声で発せられた錦の言葉に、遂に芽は堪えきれなくなって、大声で笑い出した。
それはそれは、広場で錦の横に座っていた可憐な女の子と同一人物とは思えない、豪快な、それはそれは男勝りな笑い方だった。
「え、あれ、ん、あれ? え、あれ?」
芽の豪快な笑いにつられるように、錦も引き攣りながら、乾いた笑いを浮かべた。
ひとしきり大声で笑った後、彼女はお腹を押さえながら錦の肩を叩いた。
「少年よ。そろそろ気づきたまえ」
「え、なに。え」
ニヤリと不敵に笑う芽の瞳に錦がパニックを起こしていると
「まぁ、入れ入れ」
部室の扉が突然開かれ、これまた軍服姿の男が大きな声を上げながら、一回生らしい男子をつれて入ってきた。
「ん? 君は誰だ」
「いや、僕は」
「体験入部希望者よ」
「え?」
驚いて振り返る錦に芽はウインクを送った。
えぇぇえええぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ。
「おお、そうかそうか。君もか。俺は五回生の林だ。よろしくな」
「え、あ、はい」
林のテンポに巻き込まれ、状況に流されやすいのか、錦は差し出された林の右手に無意識に握手していた。
「とりあえず、一人確保って言うことで、アタシのノルマは達成ですね」
「ど、どういうこと?」
「だからそういうことだよ。山田くん」
芽はまたニヤリと笑うと錦がさっき書いたノートの表紙をパンッと叩いて指さした。
"サバイバルゲーム研究会、体験参戦申込書"
確かにそこにはそう書かれていた。
………………お母さん。大学は怖いところです。
|
|